調和神宮の地下深く。
聖域の最奥。
幾重にもかけられた封印の扉の向こうに、小さな祈りの間があった。
「ここは、いったい……」
こんな場所など、見たことも聞いたこともない。
修行を抜け出して散策に励んでいたので、天空殿の隅々まで知っていると自負していたのに。
しかも、封印を課しているということは、危険なものを封じているというのか。
青年の心の内を知ってか知らずにか、女神は右手を掲げ、室内の水晶球に明かりを灯す。
頼りない明かりに、無数の神像が浮かび上がった。
「今は名もなき古い神々を奉った神殿です。」
ここは、代々の調和神の犯してきた『罪』が眠る場所。
『正義』の名の下に滅ぼしてきた、無数の命を忘れぬように。
形にして残してある所。
無償で得られる調和などあり得ないのだと戒めるために。
「危険なものは何一つありません。封印は、ここに在る者の眠りを守るために私が施しました。」
祭壇の上に、巨大な結晶が載せられている。
その内に眠る黒髪の少年。
十代半ばから後半といったところか。
乱れかかった前髪。
その間からのぞく表情は、怖いくらい透明で哀しくて。
膝を抱え、背を丸めて何かを堪える様は、泣いているのかと錯覚する。
「これは……」
彫像などではない。
結晶の内から、光流を感じられる。
生きた人が封じられているのだ。
「一万年前、『罪』ゆえに封印されし者。」
これでは、まるで見せしめだ。
こんな封じ方をされるとは、いったいどんな大罪を犯したのか。
内通。
反逆。
そんな言葉が似合いそうにない少年なのに。
「彼の『罪』は、『罪』ではありません。」
女神言葉に、迦楼羅王は問い返す。
「ビシュヌ様?」
女神の視線は、少年へと注がれたまま。
「同じ情況なら、誰もがしようとすることです。」
迦楼羅王は女神を見つめる。
口調からして、女神はこの少年のことをよく知っていると思われた。
外見は若くとも、この女神は一万年前の大戦を知る数少ない生き証人。
おそらく、女神は神になる前から少年のことを知っていたのだろう。
「ただ、彼の立場がそれを許さなかった。それだけです。」
女神がしばらく口を閉ざす。
当時の記憶に思いを馳せていたようだ。
「何者なのですか、この少年は。」
許されない立場と言われるくらいなら、ただ者ではあるまい。
かなり高位の武官か文官だと推測される。
おそらく、天空界の命運を左右してしまうような者。
「転生前の記憶はなくとも、覚えはありませんか。彼の称号は修羅王。」
思いがけない名に、青年は驚きを隠せない。
「修羅王というと、八部衆の?」
八部衆は、デーヴァの神将集団において、八大明王に次ぐ重要な位置を占めている。
実戦に投入される中では、最高位だ。
八部衆の中でも戦神の異名をとる修羅王は、ここ一万年の間空席のままとされた幻の神将。
現れないはずだ。
このように封印されていては、転生もできない。
八部衆は一人、または数人が交代で転生していると言われている。
前の持ち主が死なない限り、神甲冑に次の持ち主が現れることはない。
「ええ。あなたと同じ、八部衆です。」
言った女神は哀しげだ。
「彼は、私たちの過ちを許さないでしょう。それでも、今の私たちには、彼が必要なのです。
なんと誹られようとも。」
心の内で、女神は呟く。
(私は調和神なのだから……)
個人の想いよりも、一族の存続を選ばねばならない。
その運命からは逃げられないのだ。
死ぬその瞬間まで。
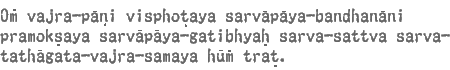
ピシッと、結晶にヒビが入る。
女神の詠唱が途切れた。
牢獄の水晶が砕け散り、残らず光流へと還ってゆく。
支えを失い、祭壇に叩きつけられる前に、迦楼羅王がその身体を受け止めた。
見た目以上に軽い身体。
(これが、戦神と謳われた修羅王なのか?)
余分な肉が見あたらず、手足もすんなりと細い。
もっとも、必要な筋肉だけは、しっかりと付いている。
無駄のないしなやかな身体だ。
意識が戻り始めたのか、瞼が震えている。
やがて、薄く開かれる双眸。
月のない夜空より黒い瞳が、ぼんやりと迦楼羅王を映している。
まだ、焦点が定まっていない。
幼げな仕草に庇護欲を刺激され、抱き締める腕に力がこもった。
途端、強い力で振り払われる。
「触れるな!」
少年は床に崩れ落ち、力が入り切らない腕で身体を起こす。
何もかもを拒絶した、闇色の瞳。
それを、傍らの女神へと向けた。
「俺は二度と起こすなと言ったはずだぞ、ビシュヌ。」
女神の表情がにわかに曇る。
予想はしていたものの、少年の怒りと絶望の深さを改めて見せつけられたのだから。
それでもここで退くわけにはいかないのだ。
調和神としては。
気を取り直し、少年の目を見つめた。
「許してとは言いません。それでも聞いてほしいことがあるのです。」
修羅王こそが、デーヴァ存続の最後の鍵。
他の誰にも代われない。
彼でなくてはならないのだ。
「たとえ、デーヴァが滅びようと、俺には関係ない。」
「分かっています。ですが、修羅王……」
「ちょっと、調和神に向かってなんて口のききようを……」
女神の名を呼び捨てるとは。
あまりのことに、迦楼羅王が憤った。
対する少年は、青年が何を怒っているのか理解できなかったらしい。
「調和神? スーリヤはどうした。お前が継いだのか。」
スーリヤとは、先代の調和神の名である。
少年は、先代をも呼び捨てた。
双眸に、深い怒りが燻ぶっている。
再度言い募ろうとする迦楼羅王を制し、女神が小さく首を横に振った。
「良いのです、迦楼羅王。」
その称号に、少年が改めて青年へと目を向けた。
「迦楼羅王……?」
訝しげに、少年が見つめてくる。
何かが違っているとでもいうかのように。
「あれから、一万年経ったの。もう、あなたの知る八部衆は一人もいないわ。
スーリヤ様も、あなたを封印した後まもなく亡くなられました。
彼らを封じ、天空界から追放するために力を使い果たされて。」
少年は拳を握り締める。
行き場のない憤りをどこにぶつければ良いというのか。
そして開いた掌に残る、血の滲む爪痕。
「そうか……」
諦観漂う横顔。
すべての気力を失ったかのように。
「何故、俺の眠りを妨げた。
また、デーヴァの手に負えないことでもあったのだろうが、生憎だったな。
俺には、デーヴァのために戦う気なんぞ毛頭ない。あのときだってそうさ。」
少年には似合わない辛辣な口調。
屈託ない笑顔こそが、似合うだろうに。
しかも、彼の言い方は、まるで彼がデーヴァではないかのようだ。
「このくだらない世界に未練なんてあるものか。あいつがいないのに、生きていても仕方ない。」
少年は、死なせろと言う。
生きる意味を見出せないから。
それにしても、あいつとは誰なのか。
ここまで、少年を魅きつけて離さない者とは。
「彼なら、生きているわ。」
両手で衣を握り締めながら、女神が告げた。
苦しげに。
「ビシュヌ?」
「夜叉王は、まだこの世界にいる。
この世界への執着が強くて、スーリヤ様の封印が充分にかからなかったらしいの。
だから、今でも苦しんでいるのよ。」
調和神は悔しげに言う。
覚悟はしていたが、修羅王と夜叉王の繋がりは生易しいものではない。
いつの時代でも。
特に、夜叉王の修羅王に対する想いは、狂気にも似ている。
「あいつが?」
強い疑念。
疑いを捨てきれない少年の様子に、彼の絶望の深さが垣間見える。
「あなたになら、聞こえるでしょう。あの風の声が。」
女神の言葉に、少年は意識を外に向けた。
一万年ぶりの外界。
風が吹き乱れている。
中でも、東方より来る風が、不穏な気配を孕んでいた。
血の臭い。
そして、見知った光流。
間違えるはずがない。
確かに、夜叉王の光流だった。
彼の得意とする技は、風を媒体としたものである。
「生きて……いるのか。」
もう、永久に失われたのだと思い込んでいたのに。
「おそらく。二日前、前線の一つが消息を絶ちました。
まだ、確証はないのだけれど、あまりにもあのときと状況が似ているのです。
彼以外に、そんなことができるとは思えません。」
女神の言葉に、今度は迦楼羅王が目を剥いた。
今の言い方では、まるで『夜叉王』がデーヴァの軍を襲ったかのようではないか。
夜叉王は、修羅王同様に八部衆の一人。
デーヴァ神軍の要の神将。
敵であるはずがない。
あってはならないのだ。
「お前だけだったな。あのとき、俺の話を聞いてくれたのは。」
少年の声が和らいだようだ。
先刻までにない、温かみを感じられる。
大切らしい相手は、敵であるかもしれないというのに。
「で、どうしてほしいんだ? 俺にあいつと刺し違えろとでも?」
俺はそれでもかまわないが……
少年の瞳はそう語っていた。
殺し合いでもかまわない。
あいつと向かい合えるならと。
同じ時間、同じ世界に存在していることが、一番大事なのだ。
「死んではだめです。」
女神がやや声を荒げた。
少年の言葉が本気だと知っているから。
「ただ、彼を……止めてほしいの。あのままでは、哀しすぎるわ。」
そう言って、少年の左肩に手をかざす。
一万年経っても、いまだに治りきらない傷口に。
仄かに温かい光。
少年は女神の細い腕を振り払った。
「触るな!」
一瞬、少年の瞳に金の光が宿ったように見えた。
目の錯覚だろうか。
「気持ちは分かってるけど、痛いでしょう。戦いに支障も出るし。」
少年は、断固として首を縦に振らなかった。
「あいつのつけた傷だ。勝手に消すわけにはいかない。なんといっても、あいつのことだ。これがなくては、俺だとは信じないだろう。」
言われて、女神も夜叉王の性格を思い出す。
妙に律儀で、頑固で、融通のきかない上に、扱いにくい人物だった。
自由奔放な修羅王とは別の意味で、上層部に倦厭されていたと聞いている。
女神が深く息をつく。
仕方ないとでもいうように。
「分かったわ。傷は消さないから、治療だけでもさせて。詳しいことは、その後に話すから。」
今にも開きそうな傷口というのは、見ている方がつらい。
調和神が引き連れて来た少年を目の当たりにし、雷帝は苦い顔を隠さなかった。
一万年以上生きる彼は、修羅王を知っている。
「ビシュヌ様……」
いつもは穏やかに微笑んでいる女神であったが、雷帝にみなまで言わせない。
「修羅王が行ってくれるとのことです。」
雷帝が反対するのは、目に見えていた。
雷帝だけではない。
一万年前の事実を知る者なら、誰もが反対するに違いない。
「しかし、彼に兵をまかせるのは……」
「安心しろ。俺一人で充分だ。」
デーヴァの貴重な戦力を割く必要はないと言う。
「修羅王!」
「足手まといはいらない。俺たちの邪魔をするような奴もな。」
修羅王の挑むような瞳。
鋭い眼光が、二度目はないと語っている。
「そなたに、奴が殺せるのか。」
雷帝の嘲笑うかの言葉に、修羅王は笑み返す。
「俺をそこらのデーヴァと一緒にするな。俺は逃げたりしない。奴の前に立ち続けるだけだ。
命ある限り。」
自分を殺していいのは夜叉王だけ。
それが約束だった。
そして、あいつを殺していいのも自分だけ。
他の誰でもない。
自分でなければならないのだ。
「死なないでください。修羅王。」
女神の言葉に、少年は首を横に振る。
「それは約束できない。ただ、たとえ俺がどうなろうと、お前は介入するなよ。」
二度目は許さない。
久方振りの逢瀬なのだ。
邪魔はさせない。
たとえ、神であろうとも。
|
|
<<Back
|
|
Next>>
|
<お手数ですが、メニューに戻るときはウィンドウを閉じて下さい>